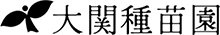Vegetable野菜の栽培ポイント
ネギの栽培ポイント
苗の植えつけは春(3月中旬〜4月下旬)か夏(7月上旬〜8月上旬)。
深植えにするので、土壌の性質が著しく生育、収穫量に影響します。軟白部をより長くおいしく育てるには、通気性、水はけ、保水性がよく、土寄せしたときに土崩れしにくい土壌であることが大切です。
連作障害は少ないですが、できれば1〜2年、あけた方が生育がよくなります。
タネまきは、3月下旬〜4月上旬(春まき)か9月上旬〜10月下旬(秋まき)にします。
苗床として、幅50〜60cmの平畝をつくるために、植えつけの2週間前までに、苦土石灰を1m2当たり200gを畑全体に散布して、よく耕します。植えつけの1週間前、1m2当たり堆肥2kgと粒状肥料を1m2当たり200g施します。その1週間後に畝を立て、10cm間隔に深さ1cmほどのまき溝をつくり、1cm間隔にタネをまいて覆土します。
発芽したら3cm間隔に間引きます。草丈が10cmほどになったら土寄せを行い、液体肥料か、液体肥料を500倍に薄めて、1週間間隔で2〜3回追肥します。さらに草丈が30cmほどになったら、同様に追肥と土寄せしましょう。
草丈が40〜50cmになったら、苗の植えつけ適期です。
植えつけは、春(3月中旬〜4月下旬/秋まきのもの)か夏(7月上旬〜8月上旬/春まきのもの)購入した苗、あるいはタネから育てた苗を用意します。畑や菜園は、植えつけ用の深い溝をつくるために、耕しません。
幅90〜100cmの区画をとり、中央に幅15cm、深さ20〜30cmの溝を掘ります。ネギの軟白部の長さは、この溝の深さが勝負になります。
次に、溝の壁に、苗を5cm間隔でまっすぐに立て、根の部分を土で軽く押さえます。根元にワラを、先端が互い違いになるようにしてたっぷりとかぶせ、苗を安定させます。苗の植えつけ後、水やりは不要です。
水やり
葉がぐったりとしおれない限り、水やりは不要です。
植えつけの2〜3週間後から収穫の1カ月前まで、4回程度に分けて土寄せします。1回目の植えつけ後2〜3週間後、苗が根づいたら、苗の植えつけ時にかぶせたワラの上に、粒状肥料を1m2当たり200g、パラパラと均一にまきます。さらに苗の分かれ目ぐらいまで、土をかぶせます。以降、月1回に同様に土寄せします。最後の土寄せは、5月頃(秋まき、翌春植えの場合)、10月頃(春まき、夏植えの場合)です。収穫はその1カ月後が目安です。軟白部が40〜50cmになったら収穫できます。埋めた溝の部分を掘り起こし、反対側からも同様に掘って、長ネギを引き抜きます。☆ さび病
初期症状として表面にオレンジ色の小斑点がでる。
激発すると全体がさび色に覆われ被害部は枯死する。※ 病気以外に害虫発生の時期ですので、予防剤・治療剤等何でも
お気軽にご相談ください。

カリフローレ栽培
 |
スティックカリフラワー カルフローレ栽培について
(播種)
発芽適温は18〜25℃です。育苗を行う場所は、日当たり風通しの良い場所で行います。
高温時には遮光(50%程度)を行い、地上部の日焼けを避けるようにします。
発芽後の潅水で、子葉展開時の水分過多は、胚軸が伸び徒長の要因になるので注意します。
(育苗)
本葉3枚程度の根張りの良い節間の詰まった茎の太い苗に育てます。
(定植)
株間35cm 畝間60〜70cmで定植します。
乾燥条件では定植後にしっかり潅水して、初期生育を促し順調な活着を心がけます。
(肥料・農薬)
10aあたりN:P:K15:15:13Kgです。
元肥主体で、生育を見ながら追い肥を施します。
生育後半に窒素系の肥料で花蕾の品質が良くなります。
酸性条件下では、根こぶ病が発生しやすく、生育不良になりやすいです。
春〜秋はアオムシなどに注意します。初期被害にあうと株が大きくなりません。
にんにく栽培のポイント
・ホワイト6片種は葉の枚数が決まっているので、早植えして年内に芽が出てしまうとトラブルになります。
・年明け2月中旬以降に芽が出ればOKです。
・鹿沼では11月15日過ぎ 早植えは禁物。
・植え付けは、種の3倍約10cm深植え。
・寒さに当たると、分球するのでハウス栽培は不向き。
・肥料は長く効く有機肥料 タケミゴールド100か追肥がいらないベストマッチがお勧め。
・追肥は3月上旬にバイオエースを根元に入れ3月中旬以降の追肥はやらない(収穫後に腐る)。
・乾燥が強い時は灌水する 乾燥に弱い。
・坊主、分球の茎は、晴天時に摘み取る。
・桜の開花から、約2カ月で収穫。葉が黄ばむ。
・収穫する頃は、気温が高く生育が早いので適期を逃さない。
・収穫したらば、すぐに根を切り落とす。
・重量の30%位を40℃風乾 10日位で乾燥させる。

秋じゃがいも栽培のポイント
●秋じゃが栽培ポイント
夏から秋にかけて栽培する「秋ジャガ」は、暑さが残る9月ごろに植え付け、11~12月に収穫する作型です。春ジャガと同様、植え付けから約3カ月で収穫できます。
秋ジャガは、春ジャガに比べて収穫量はやや少ないものの、イモのでんぷん価が高くなり、ホクホク感が増すのが特長。気温の低い時期に貯蔵するため、3カ月ほど貯蔵してもほとんど 芽が伸びず、長期間にわたって料理に利用できるのが魅力です。
栽培期間の夏から秋は、害虫発生や台風被害の危険性も高くなりますが、植え付け時期を守る、秋ジャガ栽培向け品種を選ぶなど、秋作ならではのポイントを押さえれば栽培は簡単。春ジャガとはまた違った味、食感が楽しめるので、ぜひチャレンジしてみてください。
①栽培計画
秋ジャガの栽培では、(1)秋作に適した品種を選び、(2)地域に適した時期に植え付けをすることがポイント。
栽培に適した品種を植えないと、出芽が遅れ、その後 の霜や寒さで枯れてしまいます。また、植え付け時期が早いと、暑さでタネイモが腐敗し、芽が出なかったり、青枯(あおがれ)病にかかりやすくなります。一方、植え付けが遅れると、生育後半の寒さでイモが十分に大きくならず、収量が少なくなるので注意が必要です。
植え付け適期
中間地(鹿沼地区):8月下旬~9月上旬
②タネイモの準備
秋ジャガの植え付けは、暑い時期に行うので、タネイモを切って植え付けると、腐りやすくなります。そのため、できるだけ切らずに植え付けると腐敗は少なくなります。
③土作り・植え付け
ジャガイモは連作すると、そうか病や青枯病などの土壌病害が発生しやすくなるので、連作を避けてください。畑は排水性、保水性がよく、強風が当たりにくい場所を選びます。そうか病の発生を抑えるために、1m2当たり石灰の施用量は少なめ(50g)にし、堆肥(たいひ)は500gとして十分に耕うんします。
幅60~70cmの畝(うね)の中央に深さ5cm程度の植え溝を掘り、タネイモを株間25~30cmで置きます。2~3cm覆土し、その上に化成肥料(8-8-8)を1m2当たり100~150gまき、タネイモの上に 10cm程度覆土をして畝をつくります。
植え付け後に雨が降らない場合は、水やりすると出芽が早まり、収量が多くなります。
④管理作業
生育が順調だと、植え付けの2~3週間後に出芽してきます。出芽が揃った時期(茎の長さが5~10cm)に、根張りをよくするため、除草を兼ねて株元に土寄せします。土寄せの時期が遅れると、伸びた根を傷つけることがあるので時期を逃さないよう注意します。
また、ヨトウムシ類の幼虫による葉への被害や、気温が20℃前後で降雨が続く場合には疫病が発生することがあるので、定期的に生育状況を確認し、被害が見られる場合には、早めに殺虫剤、殺菌剤による防除を行います。
⑤収穫
生育が進むと茎葉が枯れてきます。また、生育後半に霜にあい、茎葉の一部が枯れる場合があります。しかし一部の茎葉が枯れていても、イモは大きくなり続けるので、 収穫は茎葉がすべて枯れる12月ごろを目安に行います。地域によって、地表面近くは氷点下になることもあるので、その場合はイモの凍結を避けるために早めに収穫します。腐敗防止のため、収穫は晴天が続き、イモに土がつきにくい状態で行います。土が湿った状態でイモを収穫した場合には、風通しのよい場所でイモの表面を乾燥させます。

ラッキョウ栽培
ラッキョウは寒さに強く、土壌の適応性も広いため、全国各地で栽培が出来ます。病害虫の発生も少なく育てやすい野菜です。
鱗茎と呼ばれる球を植えつけますが、収穫まで約1年かかるので栽培する場所に注意しましょう。
収穫は翌年の6月ごろで、ラッキョウを若取りしたものを日本ではエシャレット(エシャロット)と呼んでいます。本来のエシャレットは、玉ねぎの一種です。
また、1年目に収穫せず、そのまま畑に残して2年目以降に収穫すると、小粒のラッキョウをたくさん収穫することが出来ます。
・土づくり、畝立て
1?当たり苦土石灰100gをまき、30cmくらいまで深く耕しておく。植えつけ1週間前には、1?当たり完熟たい肥1〜2Kg、化成肥料(8−8−8)80gをまき、土とよく混ぜる。1条植えの場合は畝幅60cm、2条植えでは80cm、いづれも高さ10cmほどの畝を立てる。
・植えつけ
種球は、20cm間隔で2球づつ、球根の先端がわづかに見えるくらいの浅植えにする。2条植えの場合は、条間を40cm確保する。
・追肥
芽が出たときと、翌年2月ごろの計2回、1?当たり化成肥料を50gほどまいて土寄せする。
・収穫
葉が枯れて、晴天が続いた時にスコップなどで土を掘ってから収穫する。
※エシャレット(若どりラッキョウ)の栽培方法
ふつう栽培と同じように植えつけます。植えつけの2か月後から、20日に1回のペースで2回ほど化成肥料(10-10-10)40gを追肥します。追肥後、葉鞘を軟白するために株元に10cmほど土寄せし、葉が柔らかい11月〜翌年4月に収穫します。
◎ラッキョウの利用方法
漬物(塩漬け、甘酢漬け)
きれいに洗ったラッキョウ1Kgに対し、塩100gの割合で塩漬けにします。2週間ほどして発酵してきたら、一昼夜流水で塩抜きし、自分好みの濃さの塩水や甘酢などで漬け直します。